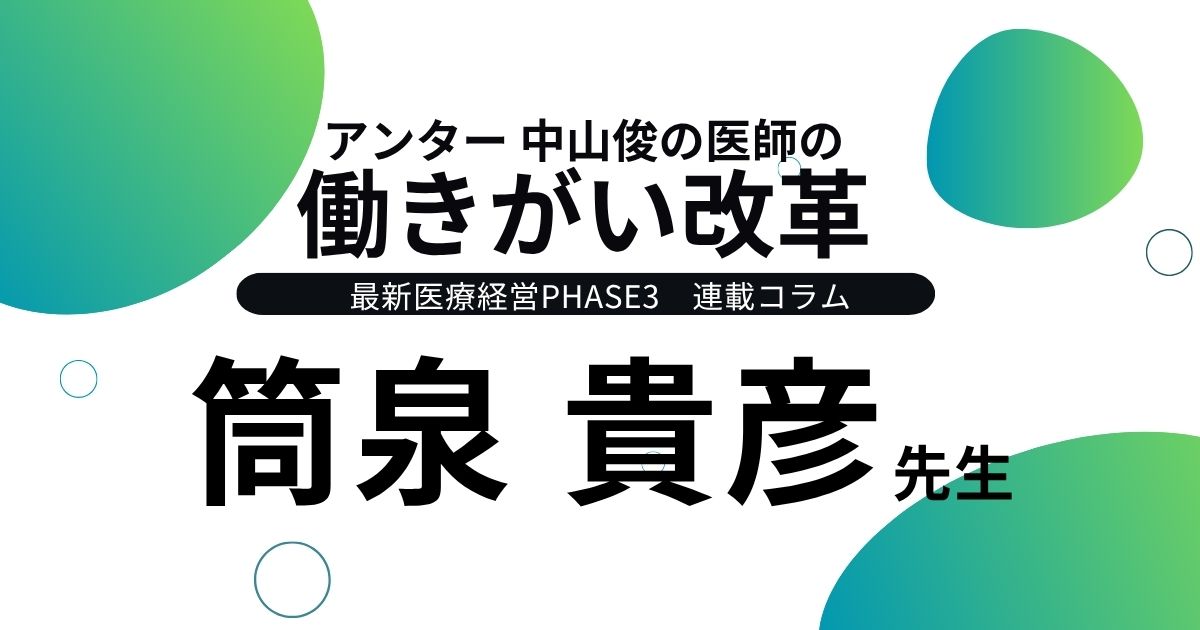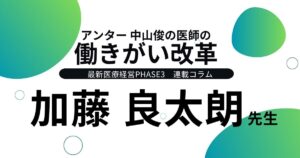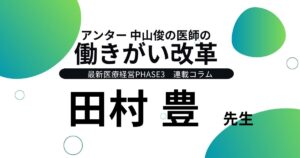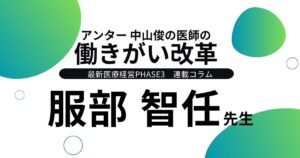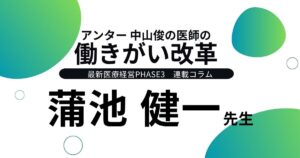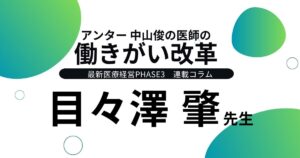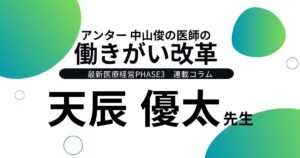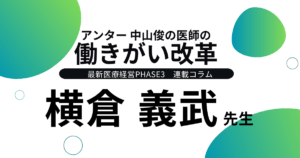筒泉 貴彦 社会医療法人愛仁会高槻病院総合内科主任部長
今回のテーマは、病院における総合内科の役割やあり方。そのパイオニアの一人であり、後進の育成にも大きな影響を与えている、社会医療法人愛仁会高槻病院総合内科主任部長の筒泉貴彦先生に、総合内科による医師の働き方改革や働きやすい環境づくりなどについて話を聞いた。


『最新医療経営PHASE3』2024年8月号(発行:日本医療企画)
医療現場を変えたいと 総合内科を志向する
中山 練馬光が丘病院や高槻病院などで総合内科の立ち上げをされてきましたが、そもそも、なぜ総合内科を志向されたのですか。
筒泉 きっかけは、ハワイ大学の医学生のときの経験です。朝5時に出勤してテキパキと仕事をこなし、昼すぎには当直担当の医師に引き継いで帰宅する。非常にシステマティックな診療を目の当たりにして衝撃を受けました。こうした経験から、いつか米国留学をしたいと思い、日本で医師としての研鑽を積みながら留学の準備を続けていました。念願のハワイ大学内科レジデントプログラムに入ることができ、3年間の内科全般のトレーニングを受けることができました。帰国する際、ハワイ大学の先輩の藤谷茂樹先生(現・聖マリアンナ医科大学教授)から「東京で総合内科を立ち上げるので手伝ってほしい」と誘ってもらいました。
練馬光が丘病院では当時、総合診療部で100人程度の入院患者さんを診ていました。忙しい毎日でしたが、「どうすれば質を高めながら早く帰宅できるか」を議論し、トライ&エラーを重ねながら、サインアウト制(病状悪化の懸念がある患者を当直医に申し送り、主治医は帰宅する)を導入したほか、休日は必ず休めるようにもなりました。
総合内科主導で進める 適材適所の役割分担
中山 医師の働き方改革の先取りですね。総合内科の役割やその重要性についてはどう考えていますか。
筒泉 医師の労働時間が長い理由の1つには、業務内容が適材適所になっていないことがあると思います。多くの疾病を持つ高齢患者さんをどの診療科が診るのかが、きちんと決められていません。ここに病棟・外来で幅広い診療ができ、かつ各疾病・病態を包括的に診療できる総合内科がいれば、割り振りがスムーズにできます。
当院では総合内科と他科が受け入れる症例の境界線を決め、役割分担をしています。誤嚥性肺炎は総合内科、間質性肺炎は呼吸器内科といった具合で、整形外科の大腿骨近位部骨折は総合内科が主科としてすべて対応しています。転倒骨折する高齢者は、フレイルで複数の内科疾患を持っていることが多い。「骨折だから整形外科が主治医」は酷な話で、総合内科が、整形外科が担当くださる手術以外の管理をさせていただくことが良いのではと考えています。
また、病棟診療を行う内科医(ホスピタリスト)が入診療を行うことで、在院日数短縮や手術待日数の減少などは海外では論文報告されており、病院経営的にも大きなメリットがあると思います。
中山 整形外科としては非常にありがたいことです。総合内科と他科が担当する症例の線引きはどのように決めているのですか。
筒泉 私が入者の振り分けを毎朝行っていますが、各科の体制やニーズなどを踏まえて柔軟に対応しています。また、人員体制や各人の能力、他科のニーズをみながら、毎年度更新しています。
中山 総合内科の現場ですんなり受け入れられましたか。
簡泉 最初は、総合内科がそもそもどのような料なのかも理解されていなかったため、”友だちのいない転入生”のような感覚でした。「まずは信頼を得ること」からと考え、パフォーマンスを高めることと、相手のニーズを考えることから入りました。当時、当院には、誤嚥性肺炎と感染症で運ばれてくる高齢患者さんが多く、現場がかなり疲弊していました。そこで「誤嚥性肺炎はすべて総合内科で診ます」と宣言したところ、拍手喝采を受け、信頼を勝ち得るにつれて「総合内科で診てもらいたい」という症例が増えていきました。その結果、内科では最も入院患者数が多くなっています。
総合内科設置には「総合内科に何を求めるのか、アウトカムは何か」を互いの立場で理解することが肝要だと思います。なお、当院では、「患者さんが幸せになれる」をアウトカムとしています。
「早く帰れる」が業務改善の工夫につながる
中山 働き方改革について何か工夫されていますか。
簡泉 当直明けは必ず帰ることにして、「8時半~17時半」動務を[7時半~16時」に変更し、仕事が終われば必ず定時で帰れるようにしました。”病院あるある”ですが、夕方に会議を設定するようなことはしません。「早く終われば早く帰れる」とみんな早く終わるよう努力します。実際、業務効率は明らかに上がり、時間外労働も減りました。
また、総合内科では「各医師が担当する入院患者は最大10人」「外来は週に初診、再診それぞれ1回ずつ」「当直は月3回」と労働量を決めています。労働量を明確にすると工夫に対するモチベーションが高まるからです。仕事効率が上がって時間的余裕が生まれた医師に対し、もっとノルマを上げるのは良くないと思っています。各医師が十分な業務を行ったうえで時間的会裕が生まれた際は、自身の研究や研鑽に使えるようにしています。たとえば能力の高い医師の場合、4時間で仕事を終えられることもありますが、「あと5人診てください」とはしません。優秀な医師がどんどん働かされ最終的に疲弊し辞めることがありますが、そんな事態を回避したいからです。
中山「みんなで助け合うのがチーム」と、一番できる人に負担が集中し辞めてしまうのは、”病院あるある”ですね。総合内科の役割はもちろん、リーダーのあり方も学ぶことができました。ありがとうございました。

筒泉貴彦
社会医療法人愛仁会高槻病院総合内科主任部長
2004年、神戸大学医学部卒業後、同大学医学部附属病院で初期研修。淀川キリスト教病院等を経て、09年、米ハワイ大学内科レジデントプログラムに留学。12年に帰国後、練馬光が丘病院でプログラムディレクターとして総合診療科の立ち上げ、15年、明石医療センター総合内科の立ち上げに従事。17年より現職。総合内科専門医、米国内科専門医、米国内科学会上級委員。編著『総合内科病棟マニュアル』 (MEDSI)、『THE内科専門医問題集 【WEB版付】』『THE内科専門医問題集2【WEB版付】』(いずれも医学書院)。
(『最新医療経営PHASE3』2024年8月号 発行:日本医療企画)