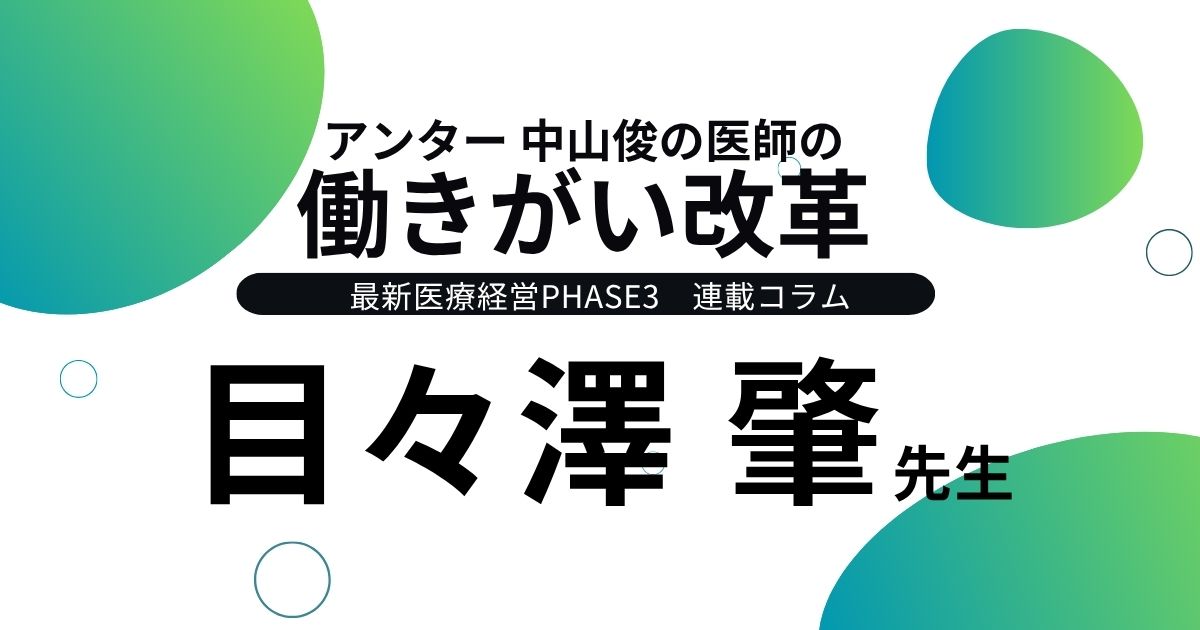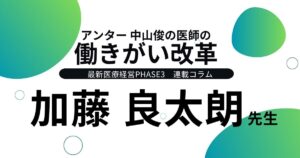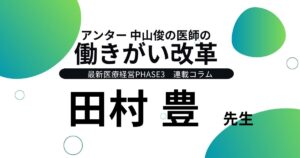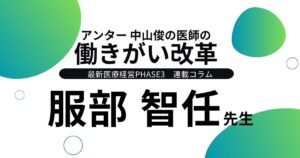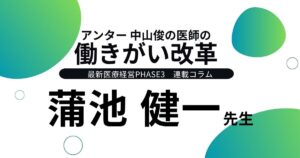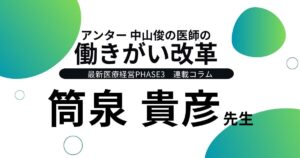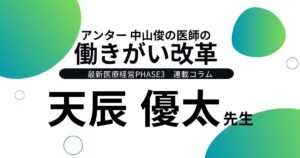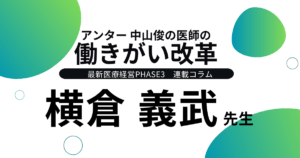目々澤 肇 目々澤醫院院長
今回は、研修医の頃からIT活用を独力で進め、現在は東京都医師会の東京総合医療ネットワークの旗振り役も務めるなど、東京都の医療DXの第一人者とも言える目々澤醫院の目々澤肇院長と語り合ってもらった 。
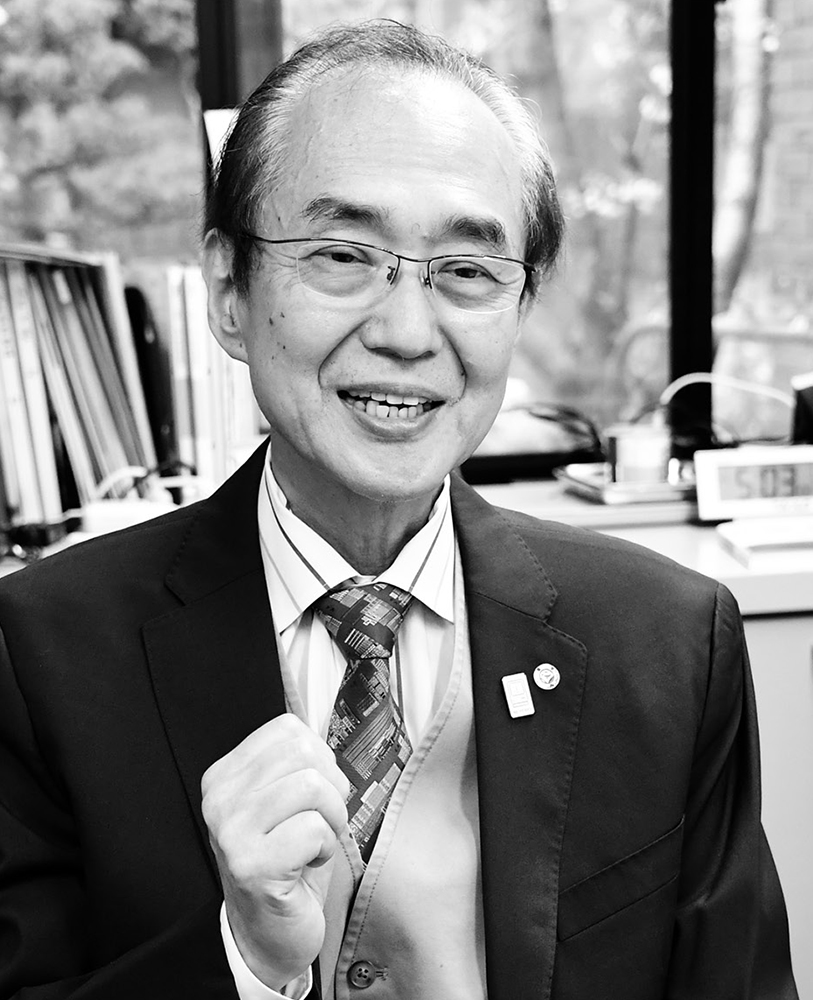

『最新医療経営PHASE3』2025年6月号(発行:日本医療企画)
診療の傍らで培ったIT感覚
中山 コロナ前以来、久しぶりの再会になります。まずは、先生のITとのかかわりについてお聞かせください。以前よりお話をうかがっているのですが、医師でありながらSE(システムエンジニア)のようなことまでされていたのではないかと思うほどです 。
目々澤 コンピュータに本格的に取り組んだのはスウェーデンでの留学中のことでした。研究データの処理を目的に、PC-9801nにMS-DOSとWindows3.1+MS Wordをバッチファイルでフロッピー2枚分のプログラムをメモリに読み込んで現在のSSDのようにして論文作成を行ってていました。脳循環の実験結果は巨大なコンピュー夕室で解析していた時代で、少しでも効率化できる手段はないかと、Basicで書かれていたプログラムを書き出して9801nに移植するなど自分なりに工夫しました。その経験が、診療所での実務にもつながっていきました 。
帰国後は父の診療所を継ぎましたが、その当時はまだ電子カルテが導入されていない時代で、診療の効率化のためにファイルメーカーを使って処方ソフトを自作しました。処方箋を作成するだけでなく、患者情報の管理など、診療情報提供作成などの機能を組み込んで運用していました 。
中山 まさに、技術を手段として使いこなす力ですね。当時としては非常に先進的な取り組みだったのではないでしょうか。こうした現場からの創意工夫が地域医療の情報基盤整備につながっているのは、非常に示唆的です。現在は「東京総合医療ネットワーク」の整備にも尽力されているとうかがっています 。
目々澤 東京都内の60を超える医療機関が参加しているこのネットワークでは、診療情報を安全、かつ円滑に共有できるように電子カルテ間の連携を推進しています。異なるベンダー間(現在4社が参加)の連携を図るためネットワーク全体を纏める名寄せサーバーの導入に真っ先に取り組みました 。200万円ほどの費用がかかりましたが、東京都医師会が全額を負担しました 。さらにベンダーを越えて画像閲覧ができる機能も実現できました 。国の医療DXの施策によって3文書6情報は今後閲覧が可能となっても画像共有はまだ先の話ですので、旧来のシステムによる画像連携の確保は非常に重要なことだと思っています 。
中山 現場をよく知る立場だからこその設計ですね。AI活用についても進めていらっしゃるとか 。
目々澤 はい。ChatGPTなどの生成AIは、診療情報提供書の下書きや原稿構成のアイデア出しなどに活用しています。もちろん、最終的な編集は自分の手で行いますが、思考の整理や時間短縮に大いに役立っています 。
自分らしく 働ける環境を求めて
中山 医師の働き方改革についてご意見をお聞かせください
目々澤 医師の働き方に画一的な時間制限を設けることには慎重であるべきだと思います。創造的な作業には個人差がありますし、集中できる時間帯も人それぞれです。日中に「この時間に論文を書け」と言われても私には難しいですし、むしろ、自分のリズムで取り組んだほうが良いものが書けると感じています。
「働きがい」は制度が決めるものではなく、個々の内発的な動機から生まれるものだと思います。私は、好奇心を満たし、納得いくまで向き合える環境があることこそが働きがいにつながると考えています。時間や形式に縛られすぎると、本来の力が発揮されにくくなってしまうのです。
中山 そうした柔軟な制度設計が求められますね。AIの活用も、そうした個人の裁量を支える一つの道具になり得ると思います。
目々澤 まさに、そのとおりです。ChatGPTのような生成AIは、構成案の検討や壁打ちの相手として使うことも多く、考えを深める支えになっています。限られた時間でも成果が出しやすくなる点で、働き方の幅を広げてくれているという実感があります。
中山 今後の医療制度改革におけるITの役割についての展望をお聞かせください。
目々澤 電子カルテや情報ネットワークの全国的整備は喫緊の課題です。とはいえ、導入の煩雑さやコストを現場に押しつけるだけでは機能しません。東京都医師会の医療ネットワークでも、目々澤醫院の導入システムでも、現場の手間をできるだけ省くような仕組みづくりを心がけてきました。
重要なのは、個人の最適化と全体の最適化の両立です。医師一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境が整えば、それは組織全体の力につながります。ITはあくまで手段にすぎませんが、導入の目的は、医師が力を発揮しやすくする環境を整えることにあります。医師がそれぞれのスタイルで働ける柔軟な仕組みを支えると同時に、チーム医療のなかで役割を全うできるような基盤づくりにつなげていくことが重要だと考えています。
本日は、ありがとうございました。
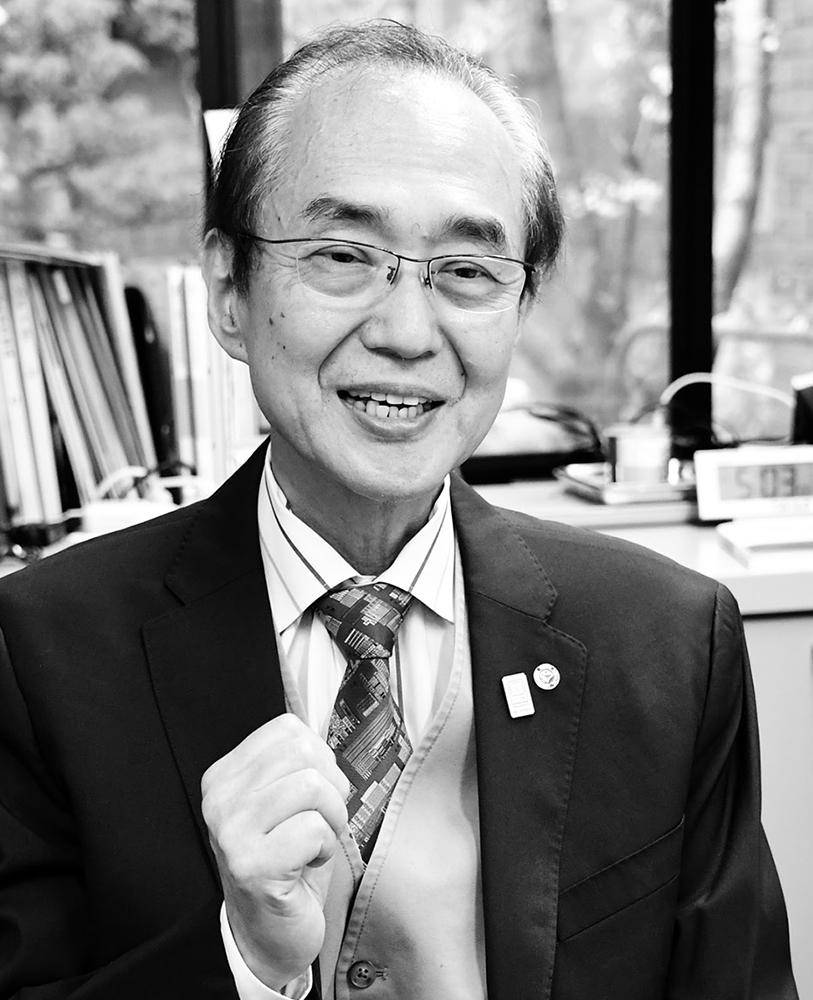
目々澤肇
目々澤醫院院長
1981年、獨協医科大学医学部卒業。日本医科大学で内科医局長・講師などを務めた後、88年よりスウェーデン・ルンド大学医学部実験脳研究所に留学し、93年にPh.D.取得。99年より目々澤醫院院長。脳神経内科を専門とし、東京都医師会理事として東京総合医療ネットワークの構築に携わるほか、電子カルテやAI問診の導入など、地域医療のデジタル化推進に尽力している。
(『最新医療経営PHASE3』2025年6月号 発行:日本医療企画)