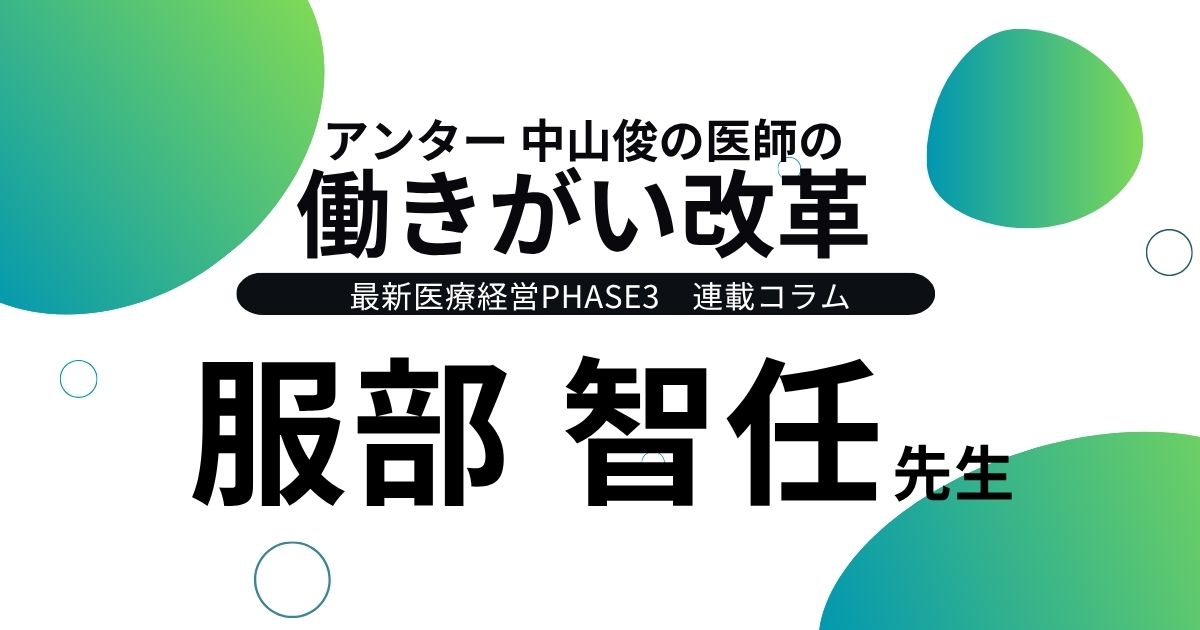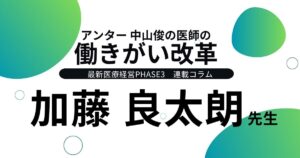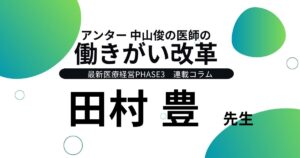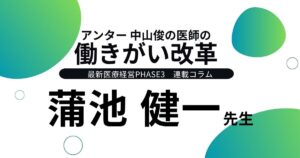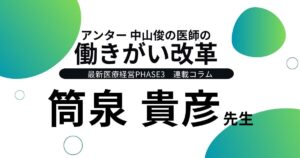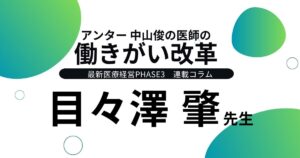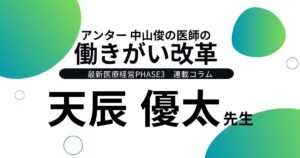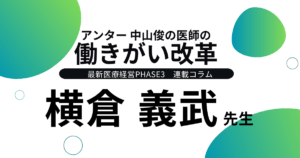服部 智任 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
海老名総合病 名誉院長
今回のゲストは神奈川県の中央部に位置し、救急医療を中心に急性期医療の中核を担っている海老名総合病院(479床)の服部智任病院長(現、名誉院長)。病院経営者の視点から医師の働き方改革に向けた取り組みの工夫などについて語り合った。


『最新医療経営PHASE3』2024年3月号(発行:日本医療企画)
診療報酬を評価指標に 求められる医療を実践
中山 病院経営者として「医師の働き方改革」をどのようにとらえていますか。
服部 時間外労働の上限規制を含めた労務管理や面接指導など、医師の働き方改革で求められる取り組みは、「やらないといけないこと」だと認識しています。ただ、見失ってはいけないのは、「自分たちの病院はどのようにありたいのか」が先にあるということです。ですから、順序としてはまず「病院のあるべき姿」を定義したうえで、これを決められた時間で実現するにはどうするか、人員を増やす必要があるのか、削減できる業務はあるのか、どのような組織に変わるべきかなど、具体的な働き方を再構築するフェイズがくるものだととらえています。
根本にある「どのようにありたいか」に関しては、地域や社会から「求められる医療」を提供することであり、そして、求められる医療とは「診療報酬点数」だと考えています。つまり、診療報酬の評価は社会にとって「よい医療」であり、医療者にとっての働くことの意味にもつながるととらえることができます。
そこで、今、あるいは将来、どのようなことが求められるのかを考えるために当院では、診療報酬改定があると該当する項目を抜き出し、医師と医事課の職員による読み込みを行っています。当初は「院長はお金のことばかり考えている」と思われていたかもしれませんが、この作業を繰り返すうちに、「診療報酬点数=自分たちの提供した医療サービスの評価」という認識が随分と浸透してきたと感じています。実際、現場では自発的に加算を算定するための取り組みを進めてくれています。
中山 病院の規模を問わず、医師の診療報酬への意識は総じて薄いものですが、簡単に意識は変わるのでしょうか。
服部 もちろん、簡単ではありません。繰り返し話をすることが大切で、オンラインで職員全員に語りかける「院長講話」に加え、年2回実施している全医師(約130人)との面談の機会を使って、対話を通じて伝えてきました。疑問を持つ人はそこで質問してきますし、こうした意見交換を繰り返すうちに、「理解したか」はわかりませんが、行動は変わってきています。なお、看護師は係長以上、コメディカルと事務職は主任以上の面談も行っています。
中山 多くの医師と面談をされるなかで感じる世代間ギャップはありますか。
服部 給与や福利厚生に関しては、若い世代のほうがシビアですね。特にZ世代は顕著です(笑)。ただ「自分の技術を高めたい」という人たちがいる一方で、「プライベートを最も大事にしたい」という人たちがいることは、世代を問わず同じだと思います。
他院との交わりなど 楽しめる仕組みをつくる
中山 医師から選ばれる病院になるためには、どのような工夫が必要だと考えていますか。
服部 働くことの楽しさを追求することだと思います。面談時には必ず、「楽しいですか」と聞いています。楽しくするための工夫の1つとして、職員を積極的に外に出しています。たとえば、VHJ機構が行っているVHJ職員交流会に研修医や指導医を参加させています。ここで研修医は他院の研修医と研修状況について意見交換し、指導医は悩みや愚痴をこぼし合ったりしながら、お互いに刺激を受けてモチベーションを高めています。また、他院と交わることで「自分たちは意外と恵まれた環境にいる」と再認識することもできます。隣の芝生は青く見えるものですから。看護師を含めた他の職種についても積極的に外に出すようにしています。
中山 「医師の働き方改革」によって、医療経営にどんな変化が起きると考えていますか。
服部 医師はもちろん、社会全体の価値観も変わると思います。1つは、医療と介護の融合です。簡単に言うと、急性期医療の価値観としては「患者さんを治す」になりますが、医療現場においても今後は「患者さんの生活は満たされているか」「どうすれば幸せにできるか」という生活寄りの発想も求められるようになるということです。
中山 医療は患者さんの問題を抽出し、それをどのように解決するかという思考になりがちですが、その人のありたい姿を支えていくという介護の価値観も求められるようになるということですね。
私は、医師にこそリーダーシップやマネジメントが大事だと考え、それらを身につけてもらうための活動に力を入れています。服部先生はそうした能力をどのようにして得られたのですか。
服部 昔から周囲の人たちが楽しそうに仕事をしているのを見るのが好きだったのです。私も外科医ですから手術が好きでしたが、1人の臨床医としてできる仕事には限界があり、医療を良くするには自分1人よりも病院全体を良くするほうがインパクトは大きい。そのためには、経営者としての力を磨く必要があると考えて、本を読んだり他の医療経営者と交流したり、学会やイベントに参加し、そこでの学びが活きていると思います。そういう意味では、好奇心旺盛な性格が奏功したのかもしれません。

服部智任
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院名誉院長
1985年、滋賀医科大学卒業。日本医科大学付属病院初期研修後、同大学泌尿器科学講座助手。米国プリガム・アンド・ウィメンズ病院、北村山公立病院泌尿器科医長、日本医科大学泌尿器科学講座講師を経て、2000年、仁愛会(現JMA)。08年、海老名メディカルプラザ院長、12年、海老名総合病院副院長、15年から現職。日本泌尿器科学会泌尿器科専門医。医学博士。
(『最新医療経営PHASE3』2024年3月号 発行:日本医療企画)